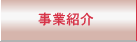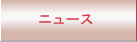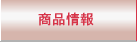和華蘭便り
和華蘭便り観光マップ
| 和(日本)・華(中国)・蘭(オランダ)文化が入り交じっている長崎のイベントや観光地の 情報をお届け致します。随時更新してまいります。 地図のボタンをクリックしたら詳細が見られます 最終更新2013年08月08日 |
 |
| 世界新三大夜景 稲佐山からの眺め | |
|---|---|
   |
長崎市稲佐町 |
|
長崎市街を見下ろす標高333mの山、稲佐山。 山頂から眺める夜景は「1,000万ドルの夜景」と称されるほど美しく、夜景の名所として知られ、函館の函館山、神戸の六甲山と共に日本三大夜景として位置づけられています。 2012年10月5日に香港・モナコと並んで 世界新三大夜景に認定されました! 平成23年4月には展望台がリニューアルオープンし、床に散りばめられた照明による光の空間がロマンティックな雰囲気を演出しています。 |
|
| 長崎ロープウェイ | |
|---|---|
   |
長崎市稲佐町—長崎市淵町 |
|
淵神社駅から稲佐山駅まで5分、15~20分間隔で運行しているロープウェイ。 稲佐山展望台へ行かれる方がよく使用されているようです。 平成23年11月にイタリア・フェラーリのデザイナーの手によってゴンドラがリニューアルしました。 そこからは展望台からとはまた違った景色を眺めることが出来ます。 夜の稲佐山ロープウェイ乗り場の通路はブルーのライトでとても綺麗です☆ 画像1*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 長崎 眼鏡橋 | |
|---|---|
   |
長崎市魚の町・栄町・諏訪町・古川町の間 |
|
眼鏡橋は長崎市の中島川に架かる石橋群の中の一つです。 寛永11年(1634年)に興福寺の唐僧黙子如定禅師(もくしにょじょうぜんじ)の手によって架けられました。 長さ22m、幅3.65m、川面までの高さ5.46m、日本初のアーチ式石橋として有名です。 川面に映った影が双円を描きメガネに見えることから「めがね橋」と呼ばれるようになり、明治15年(1882年)、正式に「眼鏡橋」と命名され、国の重要文化財に指定されました。 「日本橋」「錦帯橋」とともに日本三名橋に数えられます。 昭和57年(1982年)の長崎大水害で一部崩壊しましたが翌年復元され現在に至っています。 |
|
| 長崎 眼鏡橋 ハートストーン♡ | |
|---|---|
  |
長崎市魚の町・栄町・諏訪町・古川町の間 |
|
眼鏡橋付近の石垣の中にハートの形をした石がいくつかあります。 このハートストーン。。。 見つけてお願いをしたら恋愛成就!などといわれていて、眼鏡橋を訪れたひとはよく探されているようです。 見つけられた方に素敵なご利益がありますように♡ |
|
| 大浦天主堂 | |
|---|---|
   |
長崎市南山手町 |
|
中世ヨーロッパ建築を代表するゴシック調の国内現在最古の教会堂です。 聖堂内を飾るステンドグラスには、約100年前のものもあります。 直前に列聖されたばかりの「日本二十六聖殉教者」に捧げられました。 西坂の丘で殉教した二十六聖人へ祈りを捧げるために建てられたため正面は西坂の丘に向けられています。 設計指導者はフランス人宣教師のフューレ、プティジャンの両神父で、施工は天草の小山 秀です。元治元年(1864年)末に竣工し、翌年2月に祝別されました。 この直後の3月に、浦上の潜伏キリシタンが訪れ、信仰を告白したことにより、世界の宗教史上にも類を見ない劇的な「信徒発見」の舞台となりました。 明治8年(1875年)と同12年(1879年)の増改築により、平面形式と外観デザインも変容し、外壁も木造から煉瓦造に変更されましたが、内部空間の主要部には創建当初の姿が温存されています。 また昭和8年(1933年)に国宝となるが原爆で被害を受け、昭和28年(1953年)、日本最古の教会堂として国宝に再度指定されました。 画像3*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 長崎新地中華街 | |
|---|---|
    |
長崎市新地町 |
|
横浜、神戸と並ぶ中華街・新地は江戸時代中期に中国からの貿易品の倉庫を建てるために、海を埋め立てて出来た街です。 そして東西南北あわせて約250mの十字路は、長崎市の姉妹都市である福建省の協力で出来た石畳です。 東西南北4ヶ所の入口には朱塗りの中華門が建っており、東門には青龍、西門には白虎、南門には朱雀、北門には玄武(蛇と亀)と、方角の神である中国伝説上の動物があしらわれています。 現在、中華料理店や中国菓子、中国雑貨など約40店舗が軒を並べています。 秋の中秋節では黄色の満月燈籠が、冬のランタンフェスティバルでは赤色のランタン(中国提灯)が通りを飾り、異国情緒ただよう幻想的な世界に街を彩ります。 そして長崎中華といえばやはりちゃんぽんと皿うどんです。 独特の麺とたっぷりの新鮮野菜、魚介の風味が堪能できる食事を新地中華街のお店できっと楽しんでいただけると思います。 |
|
| オランダ坂 | |
|---|---|
  |
長崎市東山手町 |
|
オランダ坂は東山手洋風住宅群など、異国情緒あふれる東山手に位置しています。 近隣には日本で最初の女学校である活水学院・洋風住宅7棟があります。 出島に住むオランダ人の影響か、開国後も長崎の人々は東洋人以外を「オランダさん」と呼んでいたため、当時「オランダさんが通る坂」という意味で居留地にある坂はすべてオランダ坂と呼んでいたと考えられます。 現在は主に活水学院下の坂、活水坂、誠孝院(じょうこういん)前の坂がオランダ坂と呼ばれています。 |
|
| 長崎バイオパーク BIO PARK | |
|---|---|
    |
長崎県西海市西彼町中山郷 |
|
長崎県西海市にある動物園&植物園、長崎バイオパーク。 順路1周約2キロの園内には「フラワードーム」「アマゾン館」「アンデス広場」など、12のゾーンで沢山の動物たちと出会うことが出来ます。 順路を進むにつれ、動物たちの放し飼いのエリアに入っていきます。 そこでは動物たちの生活エリアに入ることで、動物に隔たりゼロで触れることやエサをあげたりすることが出来ます。 順路にも普通に動物が座っていたりするので本当に間近でふれあいを体験出来ます☆ 人間が近づいたり触れようとしても優しく接しようとすれば逃げずに、さわってもいいよ!という目を(たぶん)してくれます。 個人的にオオカンガルーには絶対に触れてみてほしいです。 可愛くて毛はふわっふわです、スタッフの方もこのふわふわ感推されていらっしゃいました。 そしてところどころに設置されているガチャポン式のエサの販売機でエサを買うことが出来、エサをもってると動物にモテます。 全国にファンが多いカピバラとも沢山ふれあうことが出来る長崎バイオパーク、とってもオススメです☆ |
|
| 長崎バイオパーク BIO PARK ☆カピバラの露天風呂 | |
|---|---|
   |
長崎県西海市西彼町中山郷 |
|
長崎バイオパークの冬の風物詩、カピバラの露天風呂のご紹介です! カピバラがゆっくりお風呂につかったりじゃれあったりする様子を見ることが出来る季節限定の特別なイベント、是非時期と時間を見計らって長崎バイオパークへ足を運んでみられてください♡ |
|
| ハウステンボス | |
|---|---|
   |
佐世保市 ハウステンボス町 |
|
ハウステンボスは佐世保市の東南152万平方メートルの広大な敷地にオランダの街並みを再現した日本有数のテーマパークです。 大村湾に面した広大な敷地の中に四季折々の美しい花々が咲き誇り、レンガ造りの重厚な街並みをめぐる運河が「本物」にこだわったヨーロッパの街並みを感じさせてくれます。 数多くのイベント、子供達の遊具も沢山揃えられていて、色んな世代の方々が楽しめる滞在型リゾートとして多くのひとに利用されています。 場内にはレストラン、ショップ、アミューズメント施設はもとよりホテル、美術館、マリンレジャーなどもあり本格的なリゾートライフを満喫できます! 季節によって違う数々のイベントを楽しむことが出来、オランダの街並みの中でいつもとは違った1日を過ごすことが出来る、花々が美しいハウステンボスへ、佐世保へお越しの際にはどうぞ立ち寄られてみてください。 |
|
| 九十九島 | |
|---|---|
   |
佐世保市・平戸市にかけての北松浦半島西岸 |
|
佐世保港の外側から北へ25km、平戸瀬戸まで連なる大小およそ208の島々を九十九島といい、島の密度は日本一といわれています。 小佐々町・鹿町町・田平町の海域を「北九十九島」、佐世保市周辺を「南九十九島」と呼び分け、それぞれ特徴があります。 北九十九島は岩肌が厳しく、南九十九島は優美でとりわけ美しい海域です。 九十九島へは九十九島観光の拠点で色々なクルーズメニューがある「西海パールシーリゾート」から遊覧船などが運航しています。 他に、市内の4つの展望台から九十九島を眺めるのもオススメです。 その中の一つ、石岳展望台からはハリウッド映画「ラストサムライ」の冒頭シーンで日本を象徴する風景として使われた海の情景を眺めることが出来ます。 画像1 2 3*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 湧水庭園 四明荘 | |
|---|---|
   |
島原市新町 |
|
四明荘は、豊かな湧き水を利用して造られた独特の風致景観から成る近代の住宅庭園です。 昭和初期に禅僧を招いて作庭したものと言われ、「四明荘」の異名を持つ主屋は、大正9年に建築されたそうです。 水屋敷として市民に親しまれてきた庭園の一つで、庭内にある池からは沸々と湧き出る大小の池が3つあり、湧水量は1日約1,000トンを誇ります。 池底はいずれも砂敷き、水は透明で美しく、護岸はごく低い石積で造られて、水中には沢飛石が配置され鯉が泳いでいます。 屋敷は、正面と左側面の二方に池に張り出す形で縁を廻していて、一段高い座敷から庭園を見下ろすような形が、座敷と庭園が一体となった景観を形成しています。 池のまわりには赤松や楓など色々な植栽が施されており、どこを見ても美しいです。 平成20年7月28日に、国の記念物に登録されました。 画像123*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 島原水まつり | |
|---|---|
   |
島原市 |
|
島原の豊かな湧き水に感謝し、水と緑のまちづくりを目指すおまつりです。 毎年8月の1日頃に三日間ほど行われています。 島原は市内のあちこちに湧水スポットがあり、湧き水を利用して造られた水屋敷も残っています。 「島原水まつり」では、全長約400メートルの街路の中央を湧水が流れる武家屋敷通りをはじめ、上記の四明荘など市内の湧水スポットに竹灯篭が飾られ、流れる清流と古きまちなみを幻想的に灯します。 その点灯式では、和太鼓の演奏、期間中は音楽イベントや夜店を楽しめます。 また普賢岳や眉山に見立てた巨大番傘のオブジェは島原の夜をさらに彩ります。 画像123*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 島原城 | |
|---|---|
   |
島原市 |
|
日向に転封となった有馬氏に代わってはいった松倉重政が島原半島運営の拠点を有馬から島原に移して、寛永1年(1624)年、7年かけて築城しました。 島原の乱で寛永14年(1637年)、一揆軍が攻撃、明治に解体されたお城は昭和39年(1964年)に復元されました。 お城の他に島原城の梅園も有名です。 島原城天守閣横にある梅園には285本の梅の木があります。 開花のシーズンには紅梅28本、白梅257本の梅を満喫することができます! 画像1 2 3*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 白木峰高原 | |
|---|---|
   |
諫早市白木峰町 |
|
諫早市北部の標高349mに位置する白木峰高原。 春の4月頃に菜の花が、秋の9月頃はコスモスが鮮やかに咲き乱れます。 菜の花は約10万本、コスモスは約20万本と一面にお花畑が広がります♡ この景色の素晴らしさを求めて1年を通じてハイキングや写真撮影に多くのひとが訪れます。 また隣接するコスモス花宇宙館では、大型天体望遠鏡による天体観測、コスモスの絵画を鑑賞できます。 画像1 2 3*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 田平教会堂 | |
|---|---|
  |
平戸市田平町小手田免 |
|
大正4年(1915年)から3年の歳月をかけ、神父と信者たちの手で建設された教会です。 正面中央部に八角形ドームを頂く鐘塔を付けた重層屋根構成の天主堂です。 重厚な赤煉瓦造りで、中のステンドグラスは荘厳な美しさで人々に感動を与えます。 世界遺産暫定リストに登録されています。 画像12*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 五島椿まつり | |
|---|---|
   |
五島市 |
|
「東の大島・西の五島」と並び称されるほど椿の自生地として名高い五島では、昔から人々の生活に椿が深く関わってきました。 そんな椿の花の見頃をむかえる2月頃には「五島椿まつり」というものが開催されます。 まつりの期間中は椿に関する展示やライトアップ、ツアーなど様々なイベントが行われています。 イベントの一つ「しまのかがり火」では、福江武家屋敷通りの石垣に並べられた灯籠が放つ幻想的な光を楽しむことが出来ます。 五島椿まつりは冬の景色と鮮やかな椿の花を楽しむことが出来るオススメイベントです。 画像1 2 3*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| 竜宮伝説 和多都美神社 | |
|---|---|
   |
対馬市豊玉町仁位字和宮 |
|
「神話の里」と呼ばれている和多都美神社。 龍神を海から神社へ迎えいれるために本殿の前には鳥居が一直線に並んでいます。 満潮時には水の中に浸かる鳥居もあるので、海中に鳥居がある風景は竜宮伝説を思わせ、神話の雰囲気を感じさせます。 そして海幸彦山幸彦の伝説の発祥の地である和多都美神社は、豊玉姫(とよたまひめ)を祭り、山幸彦が失った釣り針を求め、たどり着き、豊玉姫を妃としたと伝承される場所です。 神秘的なロケーション。。。 対馬へお越しの際には是非立ち寄ってみられてください。 画像1 2 3*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|
| はらほげ地蔵 | |
|---|---|
  |
壱岐市芦辺町諸吉本村触 |
|
おなかに穴のあいた6体の地蔵が海中に並んでいる場所があります、このお地蔵さまをはらほげ地蔵といいます。 お地蔵様の胸のところに穴が開いているので 穴があく=ほげるという意味でこの名前がついていると思われます。 壱岐のパンフレットには必ず載っているぐらい有名です。 6体のお地蔵さま、もともとは海女の守護神で、水難者の霊を慰め、疫病が流行しないように願いを込めたものだそうです。 胸に穴が開いているのは海の干満により身体の半分ほどが海水に浸かるため、お供えものが流されないようにしたものではないかといわれています。 満潮のときは頭を残してお地蔵さんは海に浸かってしまうそうです。 画像1 2*ながさき旅ネット長崎写真館様 |
|